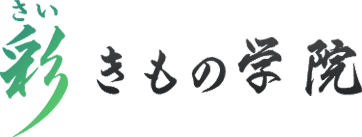
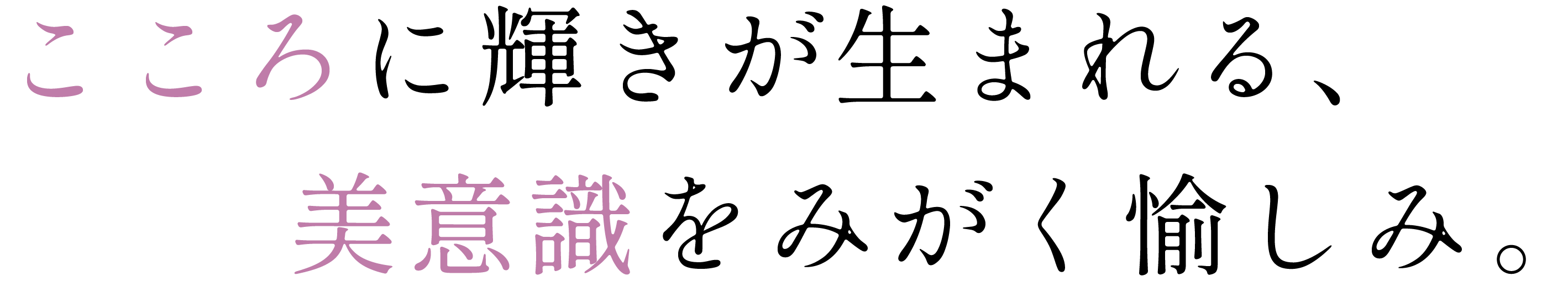
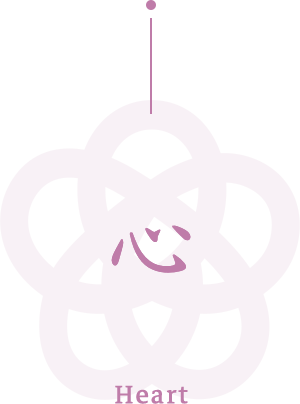
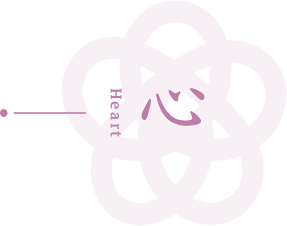
きものを装う美意識が、心を育てる。
和の価値を継承するために、
変革する。
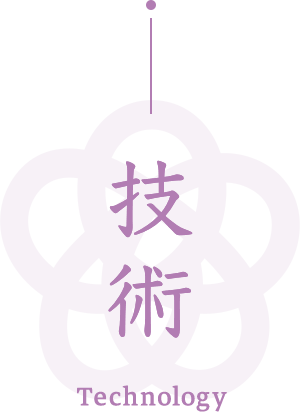
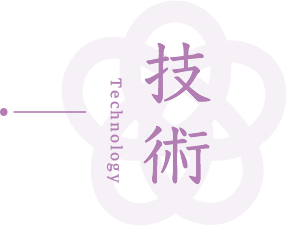
和を学び、和を拡げる。
技術を極める。
高みを目指す独自の認定制度
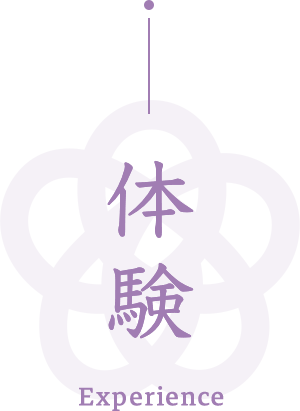
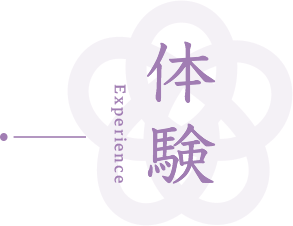
学ぶ愉しさが
向上心につながる。
安心して学び続けられる
着付け教室。
当学院は、創立当初から"衿元の美しさ"と
"着崩れしない着付け"にこだわり
本物の美しさを徹底的に
追求し続けてまいりました。
自信を持って
どんどん外に出かけてほしいから、
私たちは美しく着るための技術を
一から教えます。

きものは世界に誇れる日本の民族衣装です。後世に残すのは私たち日本人の使命です。学院は創立以来、技術(特に衿元の美しさ)にこだわり、ト ータルコーディネート、立ち居振舞、そして季節感を大切に授業に取り組んでおります。きものを通して日本の文化を学び、一人の女性として成長し輝いてほしいと願っています。あなたとの出会いを楽しみにお待ちしております。
さあ今こそご自分の為に一歩を踏み出しましょう!
大月 淑子 学院長